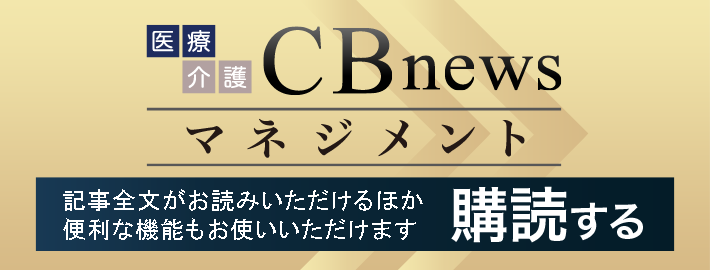医療部会(20日、東京都内)
社会保障審議会医療部会は20日に会合を開き、厚生労働省の「医療計画作成指針」などの見直しの方向性を了承した。現在の指針をベースに、医師不足の解消に向けて取り組むべき施策や、在宅医療の整備目標を立てる前に市町村と協議する方法などを追記する。同省は早ければ月内に通知を出し、改正後の指針を都道府県に示す。【佐藤貴彦】
地域の実情に応じて医療の提供体制を確保するため、全都道府県が医療計画を定めている。来年4月から次の計画期間(6年間)に入ることから、厚労省は、次期計画を作る手順や地域のニーズに見合った病床数(基準病床数)の設定方法などを決め、今年3月末に通知で示した。現在、次期計画の作成に向けて全都道府県が作業を進めている。
ただ、次期計画に基づいて都道府県が取り組むべき医療従事者不足の対策などは、厚労省が改めて通知することになっていた。
同省が月内にも出す通知では、医師の地域偏在の解消に向けて「地域医療支援センター」などが実施すべき施策を明示する。具体的には、大学医学部の「地域枠」の対象を原則として地元出身者に限定した上で、卒業後のキャリアアップの道筋を示して地域への定着を促す「キャリア形成プログラム」を、大学と連携して策定するよう求める。
また「かかりつけ薬剤師」の確保を目指して、地域の薬剤師のコミュニケーション能力を研修などで高めるよう促す。さらに、2025年時点の患者のニーズに対応できるだけの看護職員を確保するため、医療機関の勤務環境の改善や復職支援を推進させる。看護師が「特定行為研修」を地域の中で受講しやすくなるように、その研修体制の整備計画を立てることも求める。
■地域枠、「地元の人でないと駄目ではない」
20日の会合では、このうち医学部の「地域枠」について中川俊男委員(日本医師会副会長)が、「いきなり全部を地元出身者に限定すると混乱を招く」と指摘し、再検討するよう求めた。
これを受けて厚労省医政局の佐々木健・地域医療計画課長は、「地域にきちんと残る方策がセットされていれば、必ずしも地元の人でないと駄目ということではない」との考えを示し、「(通知の)書き方を工夫したい」と応じた。
(残り1183字 / 全2083字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】