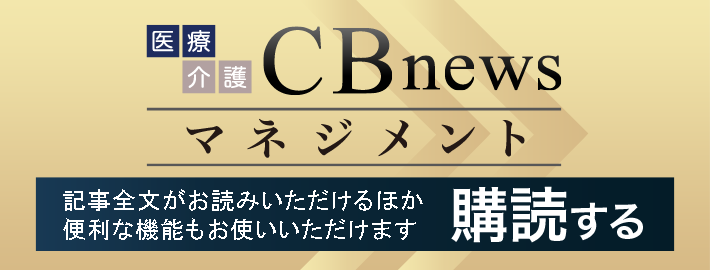入院基本料などのルールは、一病棟当たりの病床数を60床以下にすることが標準だと規定している。そこで60床刻みで病院数を集計した。その結果、「360床以上」の大規模病院を除くと、「60床以上120床未満」が252施設(16.8%)で最多だった=グラフ2=。

地方ブロック別に見た結果はグラフ3の通りで、「九州」は「60床未満」や「60床以上120床未満」など、7対1届け出病床数の規模が小さい病院が他の地方ブロックよりも多かった。

また、急性期の入院医療費が包括払いのDPC対象病院が8割超で、「60床未満」の病院に限ると非DPC対象病院が過半数を占めた=グラフ4=。

■高度急性期の特定入院料を半数超が届け出
団塊世代が75歳以上となる2025年に向けた病床再編は、▽高度急性期▽急性期▽回復期▽慢性期-の4つの機能ごとに進められる。高度急性期機能も急性期機能も、急性期の患者の状態を早く安定させるために医療を提供する機能を指すが、とりわけ診療密度が高い場合が高度急性期機能だと規定されている。
06年度に創設されてから、急性期の入院基本料の代表格として名をはせてきた7対1だが、その届け出病床が4つの機能のうちどれに当てはまるのかは明確になっていない。
一方で厚生労働省は、高度急性期機能を果たす病棟(治療室)の例に、救命救急入院料など8つの特定入院料を挙げている=表2=。いずれも、7対1以上に手厚い看護配置などを求めるものだ。

そこで、7対1を届け出る1502施設のうち、8つの特定入院料のいずれかを届け出ている病院を調べたところ、826施設(55.0%)が当てはまった。
7対1病床の規模ごとに見ると、規模が大きい病院ほど当てはまる割合が高かったが、7対1病床が「360床以上」あっても、いずれの特定入院料も届け出ていない病院が11施設あった=グラフ5=。

特定入院料ごとの届け出割合はグラフ6からグラフ13までの通り。








■総合入院体制加算、8割弱が届け出せず
急性期医療を総合的に提供する体制や、手術件数の実績などが要件の総合入院体制加算を届け出る病院の割合も調べた。同加算の主な施設基準は表3。

その結果、実績要件などが厳しい同加算1を届け出ているのは32施設(2.1%)で、同加算2は63施設(4.2%)、同加算3は229施設(15.2%)で、1178施設(78.4%)は届け出ていなかった=グラフ14=。

同加算は原則、療養病棟や地域包括ケア病棟があると届け出できないルールだが、そうした病棟を持たないのに届け出ていない病院が589施設(39.2%)あった=グラフ15=。

療養病棟や地域包括ケア病棟の併設の状況については、第2回で詳しく紹介する。
【関連記事】