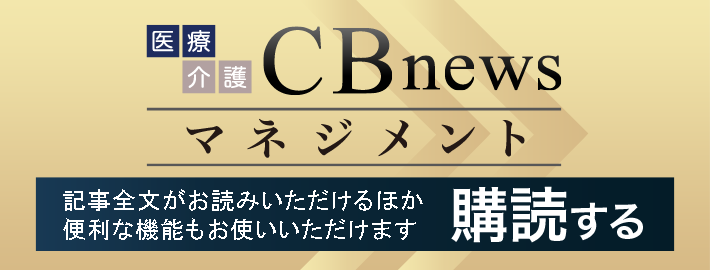長妻昭氏が厚生労働相を退き、3月で約半年が経過する。古い役所文化の改革を目標に掲げた1年間で、厚労省をどのように変えたのか。また、少子・高齢化社会に対応し得る社会保障制度への“道標”は見えたのか―。今は民主党筆頭副幹事長を務める長妻衆院議員に語ってもらった。
【このインタビューの別の記事】
「衆院選マニフェストに消費税増税を」
■役所文化の実態に驚き続けた日々
―長妻議員は「政治主導」と「厚労省改革」を標榜し、約1年間、厚労相を務めました。この1年で、政治主導による厚労省改革は軌道に乗ったと思いますか。
かなり軌道に乗りました。分かりやすい例で言えば、今、厚労省ではホームページ上で定期的に各局、各課の目標を掲示していますが、これはわたしが義務付けたことです。
そう言うと、「なんだ、そんなことか」と思われるかもしれませんが、これは大きな進歩なのです。何しろ、かつての厚労省では、省としての目標を設定したことがなかったのです。省だけではありません。局も部も課も、それぞれの目標を掲げたことはありませんでした。
わたし自身、この事実を知った時は驚きました。他の組織ではあり得ないことですからね。もっとも、驚かされたのはこれだけではありません。
国民からの苦情の内容や件数も記録せず、電話を受けるだけの職員。「責任が明確になる」と言って、利用者に対し、名刺を渡そうとしない職員。大臣の指示を「(局長など)上司の許可がない」として拒む職員―。挙げれば切りがありません。退任の記者会見でも述べた通り、厚生労働大臣になった当初は、一般社会と役所文化とのギャップに1時間置きに驚かされているようなありさまでした。
中でも仰天したのは、局長以上と政務三役が集まる機会が年に2、3回しかなかった点です。省の意思決定をする政務三役と局長以上が集まる機会がそんなに少なくては、臨機応変な対応など、望むべくもありません。そこで政務三役と局長以上が、毎週月曜に朝礼を開くことにしました。
■「無駄を削ること」を評価基準として導入
―長妻議員は、厚労省の人事制度にもメスを入れました。
従来の役所では、組織を大きくすることが評価されます。倒産することがないため、ポストを増やすことが職員の一つの行動原理になっているのです。それを改め、無駄の削減に取り組んだ人間を評価するようにしました。
具体的には、昨年7月に省内事業仕分け室の初代室長を務めた人物を官房長に抜てきしました。厚労省では初めてノンキャリアの官僚を総務課長に据えたのも、コスト意識や業務改善の意識の高さを評価してのことです。もっとも、この総務課長人事には、「総務課長以上になれるのはキャリアだけ」という不文律を壊す目的もありました。
―経歴に関係なく、誰でも出世できることを事実として示し、職員のやる気を引き出そうとしたわけですね。
その通りです。こうした努力が実を結び、わたしの在任期間中に無駄な予算カットや補正予算の執行停止、基金返上などで約1.2兆円を捻出することができました。
■前例踏襲主義を逆手に取った省内改革
―ただ、一部のメディアは長妻大臣が去った後、厚労省内部では政治主導による改革の意識が大幅に薄れたと報道しています。
その点は、大丈夫でしょう。わたしが退任しても、動き続ける「仕掛け」を埋め込んできましたから。
―どういうことでしょうか。
よく知られていることですが、役所は前例踏襲主義です。一度前例をつくってしまえば、それを着実に踏襲していく。わたしは、その点を逆手に取りました。つまり、省内の改革を推し進め、自浄作用を保つための「前例=仕組み」をつくってしまえばよいと考えたのです。
先に述べた人事も、省内事業仕分けも、課ごとの目的の明確化も、すべて同じ目的で埋め込んだ「仕組み」です。そしていずれの「仕組み」も、わたしがいなくなっても機能し続けています。国民からの苦情などのリストについても、今も毎週、ホームページ上に公表されていますし、それを基に各局がつくる「今週の改善」も毎週、公表されています。
それだけではありません。在任中、わたしは36のプロジェクトチーム(PT)を組織しました。PTの実質的リーダーあるいは副リーダーに官僚を選び、「結果を出すまで解散しないでくれ」と指示を出したものもあります。さらに、厚労省が企画・立案した政策や制度がきちんと周知され、役立っているかを調査し把握する「アフターサービス推進室」も立ち上げました。職員を競わせてよりよい政策やサービスを創出するため、「厚生労働省政策コンテスト」や「ハローワーク業務改善コンクール」「年金事務所サービスコンテスト」も導入しています。
こうした「仕組み」が存在し、動き続け、かつての「消えた年金」のような問題が発生しないようにしなければなりません。
■中医協委員から日医関係者を外した理由
―ところで、今年度の診療報酬改定は全体で0.19%の引き上げとなり、医療界は10年ぶりのプラス改定に沸きました。一方、中央社会保険医療協議会(中医協)での議論が始まる前の段階で、入院と外来の配分があらかじめ決まっていたため、中医協の委員などからの強い反発を招きました。なぜ、こうした対応を取ったのでしょうか。
社会保障における政治主導を実現するためです。
従来、診療報酬改定については、中医協に一任されていました。政治家の間で行われたのは、ごく粗い全体の報酬の方向性についての議論だけ。具体的な配分は、中医協に任されていたのです。
こうしたやり方を続けていては、社会保障における国民の声に基づく政治主導を実現することはできません。だからわれわれは、中医協の議論に先立ち、入院と外来の重点ポイントや、産科や小児科の重視といった大方針を政務三役で決めた上で、中医協での議論を開始してもらったのです。
―一昨年秋の中医協人事では、診療側から日本医師会(日医)の委員を外しました。
再診料について「なぜ診療所と病院で、点数が異なっているのか」という疑問を抱いていました。それで、委員の人選から見直すことにしたのです。当然ながら、日医からの反発は大きかったですね。従来の中医協では、大臣が委員の人事に口を出すことなど、ほとんどあり得ないことでしたから。しかし、民意と懸け離れた行政への怒りが政権交代のうねりになったことを考えると、既存のレールに乗った配分ではなく、新たな視点ですべてを見直すことは必要でした。
■中学校区を福祉自治区に-「少子高齢社会を克服する日本モデル」
―在任中、2020年の実現を目指した社会福祉構想「少子高齢社会を克服する日本モデル」を打ち出しました。この内容について、改めて教えてください。
簡単に言うと、国内に約1万か所ある中学校区を一つの単位として、新たな地縁をつくるという構想です。
地方と都市部で多少異なるものの、中学校区は、誰もがなじみ深く思える区域だと思います。その上、日本の総人口を約1万か所の校区で単純に割ると、1区当たりの人口は約1.2万人となります。住民の意見を聞きながら、一定程度の基本的な福祉サービスを提供するには、程よい規模の「福祉自治区」と言えるでしょう。
この中学校区の中で、基本的福祉サービスを受けられるようにするのです。
―それにしても、なぜ今、新たな地縁を創出する必要があるのでしょうか。
日本社会全体で、人と人をつなぐ「縁」が、薄れ始めているからです。
例えば20年後には、日本人男性の3人に1人が生涯独身と予測されます。そして、子どもを持つ家庭の3世帯に1世帯は一人親となるでしょう。つまり、この先20年で、「血縁」が結ぶ人間関係は、一気に薄れるのです。また、年功序列型の賃金体系や終身雇用が崩壊した結果、「『社員は家族』という意識=社縁」も、ほとんど消失してしまいました。さらに、自治会の活動やご近所付き合いに代表される「地縁」も失われつつあります。
そして「血縁」「社縁」「地縁」といったきずなが弱体化した結果、社会で孤立する人の数は、どんどん増えています。こうした人に、社会保障制度で一人ひとり個別に対応することは現実的とは言えません。だからこそ、中学校区という誰もがなじみやすい地域区分で、新たな「地縁」を創出して孤立している個を結び、お互いが助け合う体制を整えるべきと考えたのです。
■「長妻モデル」と「地域包括ケア」との違い
―モデルの単位である中学校区内では、具体的にどのような活動が行われるのですか。
多くの場合、校区内には診療所もあれば、保健所や介護事業所、郵便局、学校などが含まれます。ただ、相互の交流はあまりありません。まずは、そうした施設や組織の担当者を一堂に集め、連絡会を組織し、地域内の情報や社会保障上の課題を共有してもらいます。その際、拠点となるのは、自治体が運営する地域包括支援センターです。
課題の洗い出しが終わったら、次は、その課題を解決するにはどうしたらよいのか、住民の皆さんの意見を聞いて、地域ごとに福祉サービスメニューをつくる段階に入ります。具体的なサービスメニューには、特養やショートステイ、在宅診療所のほか、定期巡回・随時対応訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、訪問保育、障害者福祉施設、こども園(保育所・幼稚園を融合した施設)、精神疾患等に対応するアウトリーチ(訪問型サービス)が挙げられます。
なお、こうしたサービスはすべて行政や事業者が担うわけではありません。「新しい公共」であるボランティアや市民団体、NPOが担当することもあり得ます。つまり、政府や自治体が提供するサービスのすき間を、新たな公共で埋めるのです。
―最近、よく話題となる「地域包括ケア」と似ていますが、その違いは何ですか。
基本的な枠組みは同じです。ただ、「地域包括ケア」が介護や医療など一部の業種に限定された連携を模索しているのに対し、「少子高齢社会を克服する日本モデル」では、民生委員や郵便局、中学校など、エリアに生活するあらゆる人々が連携する点が違います。とにかく、老後、社会で孤立する人が増えれば、その分、社会保障に必要となるコストも増大します。一人ひとりの幸せのためにも、新たな「地縁」を創出し、人々の結び付きを取り戻すことが重要なのです。
―このモデルが実現しなかったのはなぜでしょう。
どんなに優れたモデルでも、財源の裏付けがなければ、絵に描いたもちで終わります。そして、財源を確保するには、首相官邸での議論が不可欠でした。それでわたしは、このモデルを実現するための精緻な議論を始めようと官邸に提案しました。
当時の官邸の反応は、一言で言えば「もう少し、待とう」。ちょうど参院選の前だったことも関係していたのかもしれません。提案への回答が出る前に、わたしの大臣退任が決まってしまった。その結果、「少子高齢社会を克服する日本モデル」は、実現に至らなかったのです。
【プロフィル】
長妻 昭氏(ながつま・あきら)1960年、東京生まれ。慶大法学部法律学科卒。日本電気、日経BP社(日経ビジネス記者)を経て、2000年6月、衆院議員に初当選。年金記録問題では、政府を鋭く追及した。鳩山内閣、菅内閣で、「脱官僚」を掲げ、厚生労働相を務めた。著書に「招かれざる大臣」(朝日新書)、「闘う政治家」(講談社)がある。
【関連記事】
「少子高齢」以外は悔いなし―長妻前厚労相が退任会見
【動画】長妻昭前厚生労働相 退任会見(全編)
新旧大臣が職員に訓示―厚労省
足立前政務官が振り返る政権交代後の1年
(残り0字 / 全4825字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。