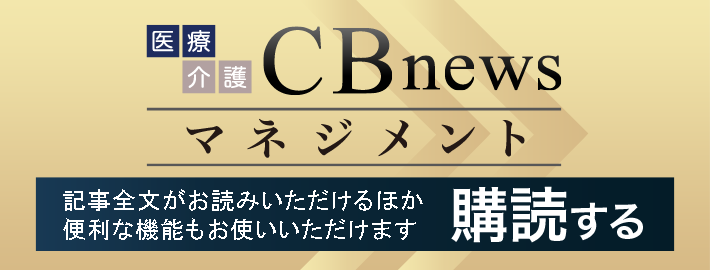旧国立がんセンターをはじめとするナショナルセンター(NC)は昨年4月、独立行政法人に生まれ変わった。各センターは、ガバナンス強化による組織改革が求められている。その先陣を切るのが、国立がん研究センターの嘉山孝正理事長だ。山形大医学部で注目を浴びた改革のスピードは速く、中央社会保険医療協議会(中医協)委員も務めるなど、その取り組みと発言は関係者の耳目を集める。そんな嘉山理事長の考える2011年とは―。
■かつてのがんセンターは要らない
―初代理事長として「すべての活動はがん患者のために」のスローガンを掲げられました。昨年を振り返っていかがですか。
山形大で医学部長をしていた時、わたしは「国立がんセンターは要らない」と言っていました。それは、センターが本来あるべき姿から遠ざかっていたためです。
がんセンターは、目の前の患者に直結するような近々の課題を解決する先端研究、先進医療が求められる組織。しかし、センターはこの10年ほど、標準化医療に向かい過ぎたために、先端医療を開拓するという義務を忘れてしまった。個々の医師や研究者、看護師のレベルは高いのに、がん医療のトップランナーから滑り落ちてしまっていたのです。高齢化が進む中、がん患者に糖尿病や循環器疾患があるのは当たり前。それなのに、余病のある患者を診る体制もないという脆弱さは、山形から見ていても十分に分かっていました。
これは、何でも厚生労働省のせいにして自らガバナンスを構築してこなかったトップの責任だと思っています。こういう状況を見て、センターが本来あるべき姿を考えれば自然、「すべてはがん患者のために」にたどり着きます。
就任後、猛スピードで改革を進めています。内科疾患のあるがん患者を診る「総合内科」(昨年10月開設)も、その一つ。また、膨大な資料すべてに自ら目を通し、人・物・カネの動きをチェックする体制を確立しました。幹部職員は任期付きの任用としましたし、医事に携わったことのない人間を医事室に送ってくるような厚労省の「回し人事」からも脱却して、独自の採用を行っています。同時に、ドクターフィー新設や看護師の増員など、スタッフの処遇改善もどんどん進めています。人は納得できれば、モチベーションも上がる。既に思った以上の経営改善の効果が表れ始めています。
―国のがん対策推進基本計画は、スタートから5年の折り返し時期に入ります。重点項目の一つでありながら、なかなか進まないがん登録について、センターが仕掛けた新たな取り組みが注目されます。
がん登録の担当者に「がん登録の目的は何か?」「なぜ、がん登録は進まないのか?」と尋ねても、明確な答えが返ってきません。がん登録が進まないのは、ずばり「誰の益にもなっていないから」です。だから、登録する人にも、される人にも、ベネフィットがあるように改革すればいいんです。
患者さんにとっての益は何かと考えれば、やはり自分の受けている治療法が良いのかどうか、がん登録の情報を活用してチェックできるということでしょう。(センターと都道府県がん診療連携拠点病院の)連絡協議会では、院内がん登録のデータを病院別に公表することを決めました。登録の精度向上にもつながるし、どの病院でどんな診断・治療が行われているかも把握できる。がん登録を進めれば、それこそ均てん化につながるというわけです。
一方で、勤務医、開業医にかかわらず、がん登録をした医師に10円でも20円でも(診療報酬が)行くような仕組みづくりは、われわれ中医協委員も頑張っていく。そうしなければ、法制度もない中で一体、誰ががん登録をするのか。誰にもベネフィットが見えない今の仕組みは、これまでがん登録が真剣に考えられてこなかったということです。
がん登録が進めば、国家としてリアルタイムにがんの情報が把握できる。どんな薬がどれだけ必要か、病床はどうか―。国家戦略がきちんと立てられます。逆に言えば、こうしたデータも、エビデンスに基づいた戦略も、国家が持っていないのが現状だということです。
がん登録や検診については、学校教育に取り入れてもらうよう文部科学省に要請もしています。このほか、センターが中心となって先端医療の開発、緩和医療の普及にも取り組んでいかなければならないと思っています。
■臨床研究の推進へ、全国ネットワークが始動
―抗がん剤などのドラッグ・ラグ解消も大きな課題になっています。
ドラッグ・ラグの実態を分析すると、欧米との差が生じている一番の原因は、治験着手までの期間にあります。日本では症例が集まらないため、このスタート段階でのラグが最も大きい。そこでセンターとしては、臨床試験(治験)の症例数を集めようということになります。
手始めに、センターと全国の都道府県がん診療連携拠点病院で「臨床試験部会」を立ち上げました(昨年10月)。部会では「臨床開発ネットワーク」(仮称)を構築します。拠点病院が互いの臨床試験に関する情報を共有化することで、無駄な重複を排除する一方、開発シーズの優先度を順位付けし、効率的に症例を集め、かつ質の高い臨床試験を推進できる。部会は、政府の医療イノベーション会議に政策提案していくだけでなく、厚労省や医薬品医療機器総合機構(PMDA)との窓口機能も持たせたいと考えており、1月にも初会合が開かれる予定です。
―臨床研究のネットワーク化については、医療イノベーション会議でも重点項目に取り上げられていますね。
ほかにも、企業の負担が大きい治験については、センターが中心となって医師主導型治験を進めたり、PMDAの相談手数料を減免したり、承認申請までを迅速化したりするシステムも必要でしょう。ドラッグ・ラグの根本的な解消には、こうした仕組みや法の整備が大前提です。従来の国立がんセンターは、厚労省の指示を受けて動いてきましたが、独立行政法人法には、政策提言の機能が義務と権利として明記されてある。がん対策が国家戦略として展開されるよう、がんの専門家集団としての政策提言をどんどんしていくつもりです。
■NC統合で「日本版NIH」を
―がん対策の国家戦略に、ほかに求められる取り組みは何でしょうか。どのような政策提言をお考えですか。
6つのナショナルセンター(国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター)を統合して、米国のNIH(国立衛生研究所)のように、権限と義務を持っている組織にしたいと考えています。「日本版NIH構想」です。
昨年5月には6NCの理事長らによる連絡協議会を開催し、統合の方向性には合意を得ています。そのキーとなるのが、各NCのゲノム情報を共有データベース化する「ゲノムバンク」の創設です。遺伝子情報の提供について、患者さんの協力を得るための包括同意書の作成を既に進めています。ゲノムバンクが形になれば、それを6NC統合のきっかけにしたいと、個人としては構想しています。
さらに言えば、がんや生活習慣病、難病などの専門家集団である各NCの機能と、国家戦略室や厚労省、文科省、経済産業省といった国の関連機能を統合して、国家的にきちんと位置付けない限り、がんセンターをはじめとするNCも、結局は「多くの病院の一つ」になってしまうと思っています。国家として、医療・医学研究に戦略的に取り組む「オール・ジャパン」の視点が必要になっているのです。
―構想を視野に、11年をどう展望しますか。
昨年は国立がん研究センターを「整地」してきました。独法化の特長は、公務員法に縛られない弾力的な人事ができること。これをフルに生かし、医師をはじめとする戦力を増強しているところです。事務部門でも正規職員を増やし、業務の質を上げる研修を充実させました。もちろん人件費比率は高くなりましたが、それはむしろ改革の証しと誇ります。昨年のレジデントの応募は、前年の約1.4倍に増えました。東病院の7対1看護も実現し、中央病院は手術件数が約1.2倍です。
こうした「整地」の成果をベースに、今年は攻勢に転じます。「みんながしたいと思ってできなかった、当たり前のこと」をしたいと思っています。
【関連記事】
がん拠点病院が治験で連携へ、ドラッグ・ラグ解消目指す
医療イノベーション担当室を設置へ-内閣官房
糖尿病あっても「がん難民にしない」―国立がん研究センターに総合内科
院内がん登録の施設別データ公表へ―連絡協が方針
NC独法化後の業務方法書案や償還計画案などを了承
(残り0字 / 全3706字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。