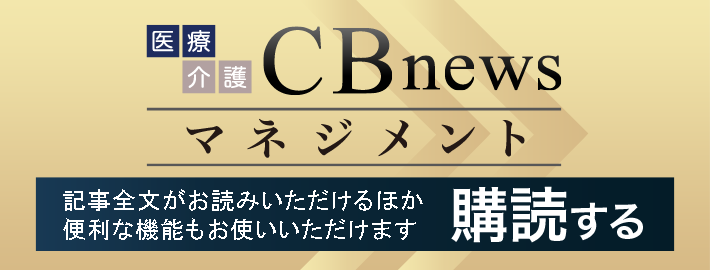【株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺優】
■厳しい経営環境下でも医療従事者の賃上げは必須
年度末、そして、新年度、初任給の大幅な引き上げや、さまざまな商品の値上げのニュースを見聞きした。この環境変化は、病院において人材確保難・コスト負担増につながり、ますます経営が苦しくなるばかりだ。
十分な人材確保のためには、まず現在働いている職員に納得感のある、他と比較し見劣りしない賃金を払うことが大事である。加えて、人材を募集する場合には、ある程度魅力的な賃金設定を行うことが求められる。
2022年10月の診療報酬改定で新設された看護職員処遇改善評価料や、24年度診療報酬改定で新設された入院ベースアップ評価料、外来・在宅ベースアップ評価料は、職員に払う賃金の原資として、患者に薄く広く負担してもらうための仕組みである。
看護職員処遇改善評価料は、その施設基準で年200件以上の救急搬送件数などの要件が求められる。そのため、すべての病院が届け出られるわけではないが、直近では3分の1の病院が届け出ている=グラフ1=。
病床規模別では、500床以上は8割以上、400床台も7割近くの施設が届け出ている=グラフ2=。
これらの2つのグラフから見えてくる看護職員処遇改善評価料の特徴として、制度開始後2年半、経時的に届け出施設割合はあまり変わっていないことが挙げられる。
■評価料20から50の施設が増え、60以上の施設が減った
看護職員処遇改善評価料は、分子「看護職員等の数」と分母「延べ入院患者数」の割合に応じて、1から165までの区分を届け出る。延べ入院患者数に対し、看護職員数の多い高度急性期病院では、一般的に評価料の区分は大きい数値になる。届け出施設において、どの区分を届け出ていたか調べた=グラフ3=。
(残り1117字 / 全1861字)
次回配信は4月16日を予定しています
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】