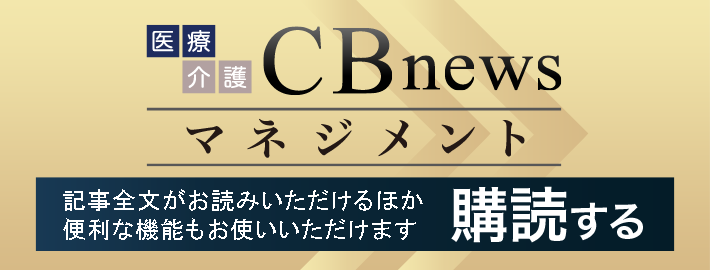【株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺優】
■高齢患者に対する「重症度、医療・看護必要度」の厳格化で7対1維持が困難に
急性期一般入院料の要件として用いられる「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)は、診療報酬改定を繰り返した結果、看護師の負担(≒提供される看護量)を表す指標から、急性期機能とそれ以外を区別する指標に変わった。2024年度改定において、患者のADL状況などを評価するB項目の廃止(7対1看護配置のみ)や、救急搬送後の評価の日数短縮は、その象徴的な事象である。負担のかかる高齢患者は、この改定で大きな影響を受け看護必要度の基準を満たすことが難しくなった。
また、これからの超高齢化や少子化の進展を見据え、国は急性期機能の集約化を図る方針である。そのため、看護必要度はさらに厳格化されることが基本路線であり、緩和されることは想定されない。一方、急性期機能、特に救急機能の集約化を図れば、基幹病院での高齢患者の増加は避けられない。制度としての看護必要度の厳格化と、看護必要度の要件を満たしづらい高齢患者の増加により、病院ではベッドコントロールと患者確保のマネジメントが重要になっている。
■未来志向で看護必要度クリアを考える
一般的に、病院の現場では、ケアの負担や医療の質を考慮し、手厚い人員配置を行いたい。また、看護配置は10対1より7対1と手厚い方が看護師確保にも有利と考えている病院が少なくない。そして、手厚い看護配置をする以上、看護必要度の要件をクリアし、人員配置に見合った入院料を算定したいと考えている。
しかし、24年度改定における看護必要度の厳格化の影響は、急性期一般入院料1の届け出施設数・病床数の大幅な減少として顕在化した。具体的には改定前に入院料1を届け出ていた約1,400施設のうち、約180施設が入院料2へ、20施設弱が入院料3へダウングレードした=グラフ1=。グラフ1の赤四角で囲んだ約100施設は、改定前に急性期一般入院料の届け出をしていたが、改定後には別の入院料などに機能転換している。
入院料をダウングレードした病院の多くは、看護必要度の要件を満たせないことが要因であると認識している。要件をクリアできなかった病院がかなり多かったということは、現状においてぎりぎり要件をクリアしている病院が相当数あると考えている。そのため、地域における急性期機能の維持・経営の維持・改善に、看護必要度の維持・向上は大きな課題であると認識している。
今月、来月の短期的な基準クリアは病院にとって死活問題である。対応は患者個別の退院調整や、診療行為の算定チェックなどのテクニカルな側面も強い。一方、まだ次期改定の具体的な議論すら始まっていない現時点において、来年、再来年という中長期的な基準クリアを考えるのは早計かもしれない。しかし、人口動態などを踏まえたデータ分析結果から病院の中長期的な取り組み余地について考える。
■50年に入院患者の増える疾患が看護必要度の基準クリアに与える影響は
(残り1657字 / 全2904字)
次回配信は5月7日を予定しています
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】