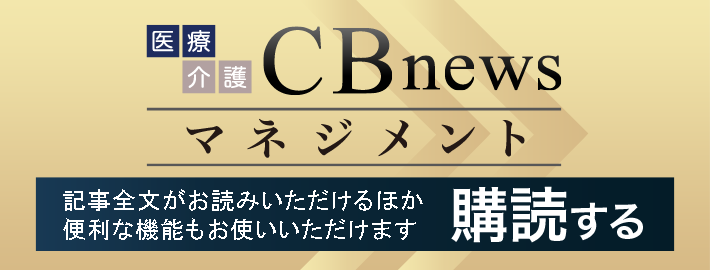【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
11月16日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、厚生労働省は介護保険施設について協力医療機関の指定を義務化する基準改正を提案した。その内容は1年間の経過措置を設けた上で、下記の(1)-(3)の要件を満たす協力医療機関を定める義務を課すというものだ。特定施設と認知症グループホームについては(1)と(2)を努力義務とすることも併せて提案した。
(1)入所者の急変時などに、医師や看護職員が夜間休日を含めて相談対応する体制が確保されていること
(2)診療の求めを受け、夜間休日を含めて診療が可能な体制を確保していること
(3)当該施設で療養を行う患者が緊急時に原則入院できる体制を確保していること
(※複数の協力医療機関を定めることで、(1)-(3)を満たすことも可)
協力医療機関を定める規定は現在も存在しているが、それと今回の案はどう違うのだろうか。現在の規定は、協力医療機関を定めてさえいればよいという基準で、協力医療機関として介護保険施設に対してどのような利便が図られるかという点は特に定めがないため、協力内容は施設と医療機関の間で定めることになる。そのため極端に言えば、医療機関の承諾を得た上で運営規定上に協力病院として名称を記載するだけでもよいわけであり、協力医療機関として特別な対応をとる定めもないケースも少なくない。
しかし、今回提案された義務化によって、上記の(1)-(3)の体制が必要になるが、その内容は特別養護老人ホーム(特養)にとって大きなハードルとなることが予測される。
介護老人保健施設(老健)と介護医療院については、もともと母体が医療機関だろうから、この体制は比較的容易に構築できるだろう。しかし特養はそういうわけにはいかない。社会福祉法人の母体として医療機関がある場合を除くと、その体制作りは外部の医療機関に理解を求めて協力を仰ぐ必要があるが、実際の運用は非常に難しいと思われる。特に(3)の「原則入院できる体制を確保していること」という要件のハードルが高過ぎる。なぜなら、この義務では協力医療機関が外部施設である特養のために空きベッドを常備しておく必要があるからだ。
■義務化なら特養は収益悪化の恐れも
(残り1264字 / 全2194字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】