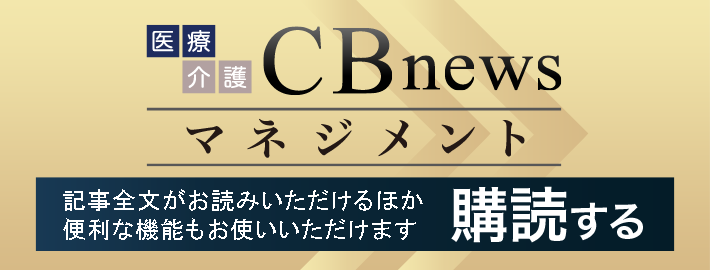基本診療料の在り方に関する議論が必要だと強調する安達秀樹委員
「中医協が改定率も適正に決める権限を持つべきではないか」―。2月10日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で安達秀樹委員(京都府医師会副会長)は、診療報酬改定の決定過程に疑問を呈した。現在は、改定の基本方針を社会保障審議会(社保審)が決め、改定率を内閣が決めて、これらを基に中医協で具体的な点数配分を審議している。しかし安達委員は、基本方針と改定率も、中医協で決めるべきだと考えている。(高崎慎也)
「プラス0.004%」というのは数字のマジック。小数点以下第3位に、切り上がらない4を付けて、公式には「0.00%」とすることで財務省の顔を立てる一方、わずかでもプラスにすることで小宮山洋子厚生労働相の顔も立てた、ということでしょう。
改定率をめぐる厚労省と財務省の折衝は、出来レースだった気がしています。政権交代した直後の10年度改定の時はガチンコで、当時の長妻昭厚労相、足立信也、山井和則両政務官が、ありとあらゆるつてを使って働き掛け、全体でプラス0.19%にしました。その時の相手が、財務副大臣としてマイナス3%を主張していた野田佳彦現首相。彼は民主党代表選の直前に、党内の議連で「基本的にマイナス(改定)はないだろう」と発言していました。あれがある以上、今回は小幅のプラス改定にすることが、早い段階で決まっていたのではないでしょうか。
この2回の改定を振り返ると、政治として医療をどう扱うか、結論を先延ばしにしたままだという印象です。薬価の引き下げ分だけを本体引き上げの財源にした、実質プラマイゼロ改定をやっている。民主党は、小泉純一郎政権が取った社会保障費削減政策を撤回することをスローガンに掲げて政権を取りました。しかし、実際に政権を取ってみたら、財務省の力が圧倒的に強かったし、党内にもさまざまな考え方があるのでしょう。中途半端な状態になっています。
―10年度とは違い、12年度改定では政府が入院と外来の財源配分を決めませんでした。
それは非常に大きいことです。今回も配分が決められれば、完全に恒常化していました。あれは明らかに中医協に対する越権行為。今回は決められたくないという思いはわれわれ診療側委員にも、支払側委員にも、厚労省保険局医療課にもありました。
最終的に阻止できた理由は、09年の政権交代以後、審議の在り方が変わったことでしょう。談合的な面を排除して、エビデンスに基づく議論を重ねていることを、財務省も認めざるを得ない状況になっています。
―2月10日の総会で安達先生は、04年の中医協改革以前のように「中医協が改定率を決める権限を持つべきではないか」と発言しました。
そこに戻すべき時期が来ていると考えています。現在、中医協ではわれわれ委員も、厚労省も膨大なデータを用意して、エビデンスに基づいた議論を重ねている。改定率の決定権がなければ、それが報われないという思いがあります。政府の中に、本当に医療のことを理解した上で改定率を決められる人がいるのかという疑問もあります。
もう一つは、診療報酬改定の基本方針。これも中医協が決めるべきだと考えています。現在は、社保審の医療部会と医療保険部会で決めることになっていますが、12年度改定に向けては、どちらの部会でも議論にかけた時間が非常に短かった。しかも、決められた基本方針は10年度とほとんど同じでした。
社保審で決められた基本方針に沿って、中医協では点数配分を決めるだけにした方が、厚労省の官僚にとってやりやすいのでしょう。しかし、基本方針を決めるプロセスが形骸化しているのなら、基本方針そのものも中医協で決めるべきではないでしょうか。そうなれば、それを基に改定率も中医協が決めるべきでしょう。
中医協で改定率を決めても、野放図に財源を求めることにはなりません。最終的には財源が絡む話だと理解する良識を、われわれ診療側委員は持っています。
象徴的なのが、答申の附帯意見に、初・再診料、入院基本料などの基本診療料の在り方について「検討を行う」と明記したこと。10年度にも附帯意見に盛り込まれていたことですが、今回は支払側の委員も「やるべきだ」と発言しています。
点数設定とは別の話として、まず評価の仕方を議論しましょう、と診療側が提案しているから、支払側も合意しているのです。今は基本診療料が何を評価しているのか明らかではないので、財源に枠がある中で、残った金で点数を決めているだけです。
―基本診療料では、安達先生は再診料が議題に上らなかったことに強く抗議しました。
診療側委員は、昨年末の総会に提出した「12年度改定に向けての意見」の中で、10年度改定で69点に引き下げられた再診料を、71点に戻すよう改めて求めました。しかし、年明けの総会に厚労省が提出した「これまでの議論の整理」には、再診料そのものの議論が明記されていませんでした。
何を評価するものなのか、明らかでない点数について議論しても、水掛け論になり、時間の無駄にしかならないと厚労省は判断したのでしょう。だからこそ、3月以降に基本診療料の在り方について議論しなければなりません。
(残り1367字 / 全3541字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】