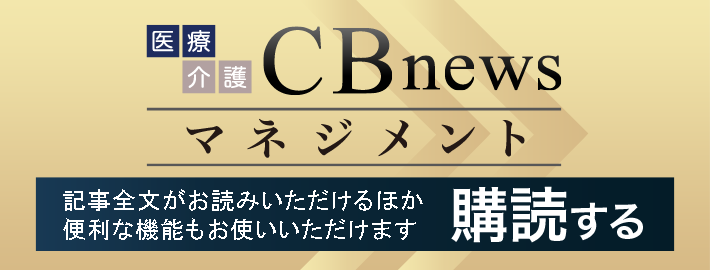【千葉大学医学部附属病院 副病院長、病院経営管理学研究センター長 、ちば医経塾塾長 井上貴裕】
この冬はインフルエンザの大流行で、どの病院も病床稼働率が高く円滑な転院が妨げられ、在院日数が長期化した傾向がある。特に高齢の救急患者が治療終了後も病床を占拠する結果、新規の受け入れが滞った事例も多い。となると、転院先がないから在院日数が長期化し、次の受け入れができないという声が上がることも当然と言える。ただ、春になり暖かくなれば病床は以前の状態に戻り、病院にもよるが高齢者救急の比率が高い病院にとっては危機的状況が訪れることになるかもしれない。
実際に病院別の自宅退院と転院患者の平均在院日数を見ると、自宅退院はおおむね1週間から10日で退院できるが、転院患者の状況は大きく異なっている=グラフ1=。自宅退院の平均在院日数が10日で転院患者の平均在院日数が20日のケースは、グラフ2でいうところの転院患者/自宅退院の平均在院日数の比率が2倍ということになるのだが、このようなケースは連携搬送を含め地域を巻き込んだ医療提供が行えている稀有な病院ということになる。

一方で、転院患者/自宅退院の平均在院日数が3倍を超え、4倍になると壊滅的であり、このような病院は地方の大病院が多く、救急の最後の砦としての重要な役割を果たすものの、新規の受け入れに支障をきたすタイミングも少なからずあることが予想される。ただ、転院患者は地域差こそあれ、全国で見ると決して多くない。自宅退院比率は80%を超え、転院率が10%を超える地域は少なく、福岡県までの6県であった=グラフ3・4=。

だとすると高齢者救急で在院日数が長引きがちな患者ばかりに着目するのではなく、予定入院で自宅退院できる患者をスムーズに帰す仕組みを優先することが最も大切なことだと私は考えている。
本稿では2022度「DPC導入の影響評価に係る調査『退院患者調査」の結果報告について」のデータを用いて転院患者の実態に迫り、これからの医療連携の在り方について私見を交えて論じる。
表1は、
(残り2187字 / 全3045字)
次回配信は3月10日を予定しています
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】