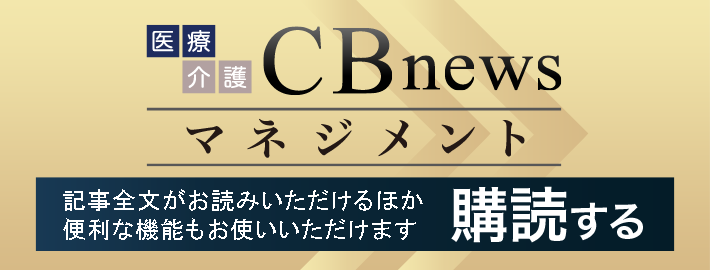医療現場などで活躍している医療情報技師の横顔に迫る新連載「病院DX推進の旗手たち」。第2回目は、大船中央病院(神奈川県鎌倉市)の放射線診断科副技師長で、日本医用画像情報専門技師会理事の青木陽介氏に聞きました。(不定期掲載)【斯波祐介】
■DXの目的を明確に
私は上級医療情報技師を持っていますが、大前提として診療放射線技師です。半日は現場で撮影、そして残り半日は画像情報管理を担っています。2003年に当院では電子カルテと、放射線・画像部門システムとしてRIS(放射線科情報システム)とPACS(医療用画像管理システム)を導入しました。情報管理の部署では文字情報の管理はしていますが、日ごろ画像を扱う業務に携わっていないと画像の異常は分かりにくいということで、画像情報は放射線診断科が中心になって管理しています。内視鏡や超音波など放射線画像以外の画像も一元管理しており、画像関連で何かトラブルがあれば、その部署がどこであれ、私が駆け付けます。
電子カルテの黎明期も今も、カルテなどの医療情報が紙から電子に切り替わる程度の変化になりがちです。黎明期の歯がゆい経験がある今だからこそ、DXを名実ともに実現するためには、患者から得られたデータをどう使うか、業務改善にどうつなげるかという視点が重要になります。
 データ活用やDXと呼ばれるものが進まない場合、「そもそも何のためにDX化するのか」という目的が明確になっていないことが理由ではないかと思っています。作りたい料理を決めてから材料を集めるように、目的に合ったツールを予算に合わせて導入していく。そのサイクルを作ることが大事です。もっと突きつめれば、「DXという言葉を使わなくても、いつの間にかDXが進んでいた」というのが理想です。気がついたら、患者の利便性が上がっていた、業務負担が減っていた、経営改善になった、ということになったら、すばらしいことです。
データ活用やDXと呼ばれるものが進まない場合、「そもそも何のためにDX化するのか」という目的が明確になっていないことが理由ではないかと思っています。作りたい料理を決めてから材料を集めるように、目的に合ったツールを予算に合わせて導入していく。そのサイクルを作ることが大事です。もっと突きつめれば、「DXという言葉を使わなくても、いつの間にかDXが進んでいた」というのが理想です。気がついたら、患者の利便性が上がっていた、業務負担が減っていた、経営改善になった、ということになったら、すばらしいことです。
そのためには、部分最適に陥らずに医療DXを進めることが大切です。医療現場の最前線にいる医師や看護師らは、目の前の患者のことをまず考えます。もちろんこれは当然なことですし、私自身も放射線技師として現場に出ているときはそうなります。しかし、それぞれの領域だけでDXを考えてしまうと全体が見えなくなってしまいます。「ある部署では満点、別の部署は0点」というのはDXとしては失敗だと私は考えています。全体を調整しながら、みんなが使えるDXを進めていくのが医療情報技師の腕の見せどころです。
■読影レポート未読管理システム
当院でのDX事例の中に、医療情報と医療安全とで連携した取り組みがあります。緊急性の高い読影レポートを読まないとレポートを読むまでカルテを操作できないようにする仕組みを導入しています。例えば、検査目的以外の所見が見つかった場合に、その読影レポートにアラートを立てます。そうするとそのレポートは緊急のレポートとして依頼医に報告され、このレポートを読んで確認し、その結果どうするかをカルテに記載するところまでしないと依頼医はカルテに復帰できないようにしました。
過去に大きなアクシデントを経験したことがきっかけで、こうしたシステムを整備し、今はほぼ100%、1週間以内に緊急レポートが確認されるようになりました。
これは情報共有の重要性を多くの部署に知ってもらう事例となりました。こういう結果を出すには、各部署のキーマンとうまく交渉することや、医師が持つ「患者を助けたい」という思いに応える、医師の困りごとに寄り添うという姿勢が大事です。医療DX事例と言いましたが、正確には「結果的にDXだった」事例です。DXという言葉を意識したことはなく、あくまで「何が問題か」「システムで何ができるか」を突き詰めていった結果がこうなっただけです。こういった事例を積み重ねていく上で、医療情報技師の役割は大きくなっていると思います。
(次回は桃仁会病院・松本清美氏です)
青木陽介 氏
大船中央病院 放射線診断科 副技師長 兼 放射線治療科
日本医用画像情報専門技師会 理事
(残り0字 / 全1688字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】