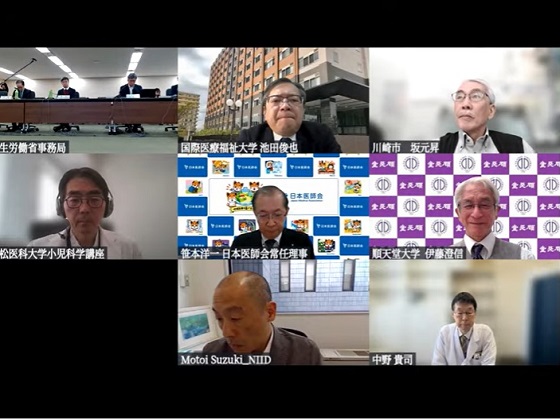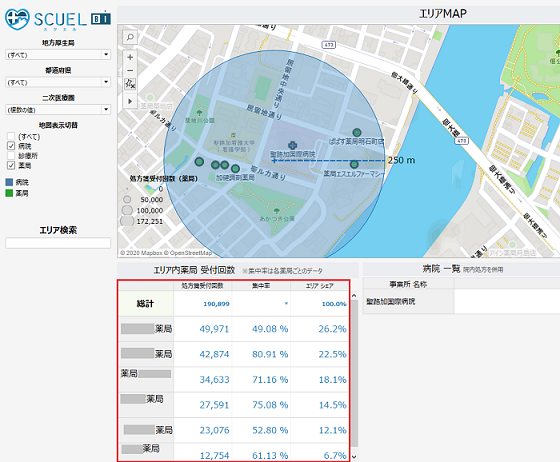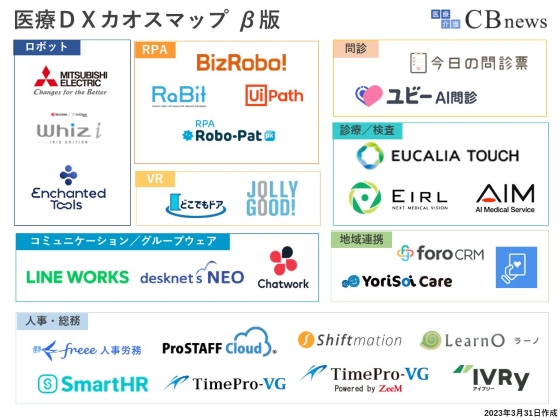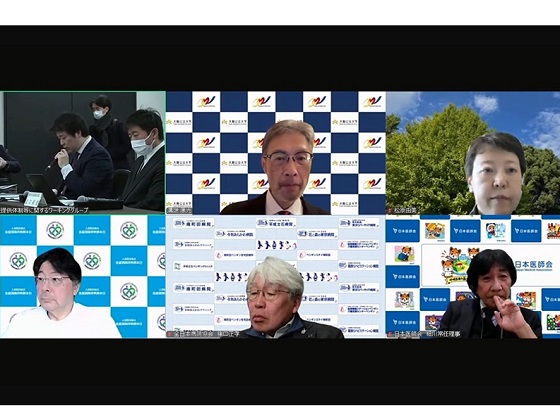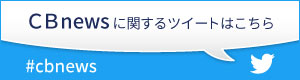たくさんの困難も人に恵まれ乗り越えられた
あの時、私はこう考えた(5)
■オランダでの論文はジャーナルに掲載 リンブルグ大病院では、指導教授との面談が週に一度あり、研究の進捗を報告する必要があった。 最初は確固たる研究テーマもなく毎日のように図書館に通い、たくさんの論文を読んだ。その一週間ごとの成果を発表しながら、最初の2カ月をかけて研究テーマを絞り、その後、実験に取り掛かるというまったくの手探りだった。 日本では臨床研究をしていたものの、リンブルグ大病院では経験のない病理学であったため、いわゆるセクション(病理組織標本)の作り方や、本格的な細胞培養、免疫不全マウス(ヌードマウス)の管理方法などの技術的な指導を受けて、研究をするための下準備をしていた。 2カ月後に研究テーマが決まった。当初、CA19-9腫瘍マーカーを研究するつもりだったが、選んだ研究テーマは、転移性モデルの作成と原発巣と転移巣の生物学的悪性度の違いをDNAフローサイトメトリーや免疫組織学的手法を用いて行う研究だ。ヌードマウスに大腸がんの培養細胞を注射して転移モデルを作り、ディプロイド、アニュプロイドに分けることにより、生物学的な違いを探るというものだ。 同時に、フローサイトメトリーに用いる材料を新鮮組織からではなくパラフィン包埋ブロックから得るなどの手法を学んだ。転移モデルについては米国ですでに、脾臓にがん細胞を注射して肝臓への転移モデルを作った研究があったが、大腸がんは大腸から肝臓に転移するものだと考え、盲腸部にがん細胞を注入し、肝臓転移モデルを作成することができた。 研究は順調に進み、大腸がんの転移モデルができたので、生物学的な違いをDNAレベルで解析をし、関川が研究室に在籍していた1年余りで一つの論文をまとめ、Invasion Metastasisに掲載された。
帰国後に関川のアイデアと指示を基に、オランダの研究室の同僚たちが、もう一つの論文をまとめた。その論文は、Virchows Archiv A Pathol Anatに掲載された。関川は、「同僚に恵まれた」と話す。 助教授だったアーレンズ氏とは今も、家族ぐるみで交流がある。アーレンズ氏は、関川が同大病院に通うために住まいを構えたグロンスフェルト村に住んでいた。そのころの思い出を聞くと、毎朝片道約10キロの道のりを自転車で共に通勤する道すがら、医学や医療の話ではなく、日本とオランダ両国の文化やヨーロッパ人の人生の生き方(the way of life)などの話をし、その後の生き方、人生の楽しみ方の礎となったという。 関川が、単独でパイオニアとして切り開いたリンブルグ大病院とのつながりは、福島県立医科大病院に引き継がれ、その後6年間、同大病院の外科学と病理学教室から、リンブルグ大病院やその関連の大学病院に研究員を送ることになった。
「あなたの転機に寄り添うサポート 医療の転職はキャリアブレイン」
以下を クリック ↓
医療介護経営CBnewsマネジメント
【関連記事】