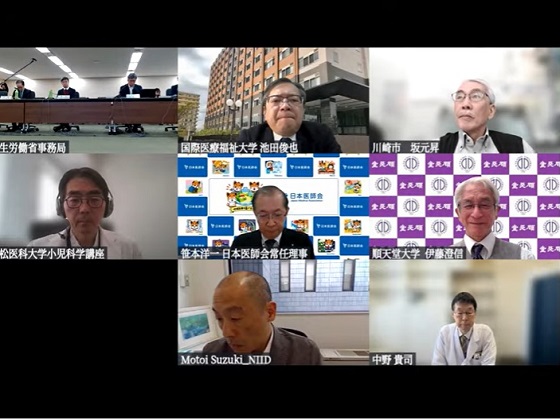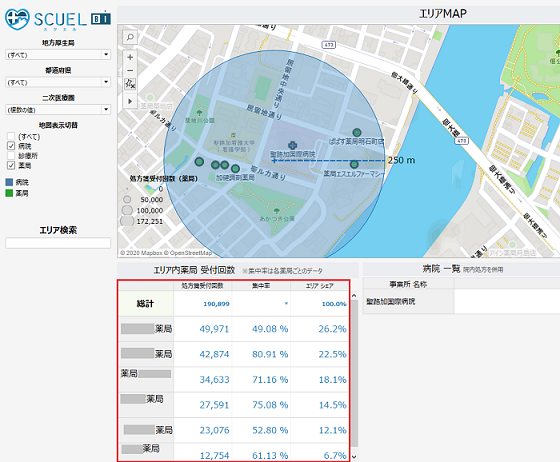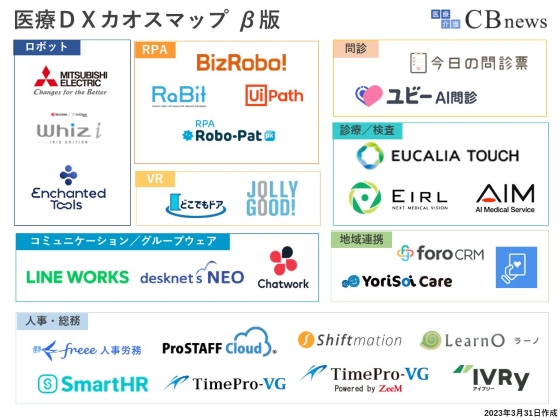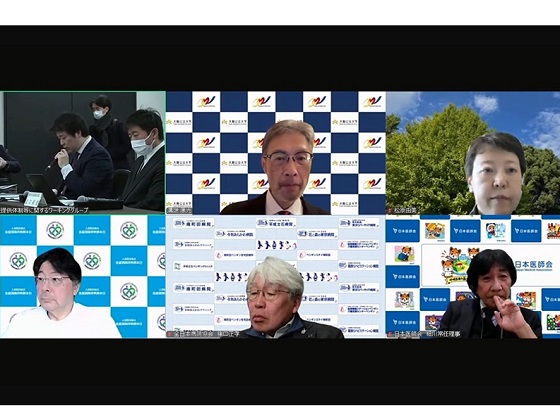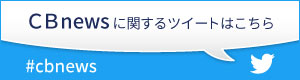弁天島で釣り糸を垂れながら
あの時、私はこう考えた(2)
■法律は独学、診療続けながら司法試験に合格 寺野は東大在学中、東大紛争の発端といわれ、後に1969年の安田講堂事件にまで発展する卒後研修医の権利を求める「インターン闘争」活動に没頭していた。当時、医学部生は卒後1年間のインターン生活の後、国家試験を受験することになっていた。その間は無給で働かされ、不安定な生活を強いられていた。寺野は、この制度の廃止を主張し、結局、国家試験を2度ボイコットしたが、最終局面で先鋭化する東大紛争には距離を置き始めていた。 医師免許を取得後に東京から移り住んだ弁天島で、臨床医をしながら弁護士になろうと決断したら、行動は早かった。妻に相談すると「後悔しないように、やりたいことをやってみて」と後押ししてくれた。寺野は「糟糠の妻って言うのですかね」と笑ってみせる。後に、寺野が米国留学する時も、小さな子どもたちと共にミズーリ大、そしてカリフォルニア大へと連れ添ってくれた。その妻は、今も現役の医師だ。 法律の勉強は独学だった。車に乗り、浜松から東京の御茶ノ水の書店に出掛け、法律書を山ほど買い込んで帰って来た。弁護士になった大学時代の友人に、司法試験のこつを聞き、自身でカリキュラムを組んだ。 そのころの司法試験の合格率は2%程度。年間約400人から500人くらいしか通過しない超難関だった。1回目の試験は、今で言う「記念受験」だった。そこで、試験の感触をつかんだが、論文の勉強だけは学校に行く必要があると考え、名古屋市内にある中京法律学校(当時)に週1回通った。司法試験合格後、米国に渡ろうかとも考えたが、妻にいさめられ、1年間考えた末、東京に戻り、最高裁判所司法研修所に入った。 ■故・唄孝一・都立大教授と出会い、今後の方向性を決めた 司法研修所での2年間の修習を経て、弁護士資格を取得したものの、迷った末、東大医学部第二内科に戻った。そこで、寺野が弁護士の資格を持ちながら臨床医として働き続ける中で、その後の考え方に大きな影響を与える1人の法学者に出会うことになる。 当時、東京都立大教授だった故・唄孝一だ。医療過誤の研究をしていた唄は、自身が卒業した東大に、医学部を卒業した後、弁護士になった「変わったやつがいる」といううわさを聞き付けて、寺野に声を掛け、そして日本医事法学会に入るよう誘った。 そのころ、医療の世界はパターナリズムという考え方が支配していて、医師と患者の立場は、医師の方が圧倒的に「上」にあり、医療過誤などへの意識は低かった。しかし、唄は時代を先取り、近い将来には医師と患者の立場は同等にまで近づき、医療過誤は無視できなくなって、医師の行動を制約するような日が来ると予測していた。 この考えに寺野も賛同した。「これからはますます、患者や国民目線の医療政策が推し進められ、萎縮医療が加速されるかもしれない」と懸念していた。唄との出会いにより、寺野は臨床医をしながら、法律家として医療事故を研究する方向を目指した。
医療介護経営CBnewsマネジメント
【関連記事】