救急ブランド化で医師呼び込む 八戸市立市民病院・今氏
「メディカル ジャパン 大阪」講演より(1) PR
3月に大阪市で開催された「メディカル ジャパン 大阪」(主催:RX Japan)には3日間で1万人を超える来場者があった。そこでは48にわたる医療・介護・薬事に関するセミナーも行われた。CBnewsは、病院経営のヒントになる4つの講演を連載で紹介する。1回目は「赤字解消に繋がる救急医療拡充 ~累積赤字135億円を解消した医療現場の改革~」をテーマに講演した八戸市立市民病院病院事業管理者の今明秀氏。
【関連記事】
2004年4月に八戸市立市民病院の救命救急センター所長に赴任した今氏。同時に臨床研修センターの所長を兼務する。救命医は今氏のみ。当時の研修医充足率は50%。「若い医師の目標を作る」として救急救命センターのテコ入れを始めた。
今氏が考えたのは「病院のブランド化」による若手医師や研修医集めだ。ブランド化の柱は▽コンセプト▽ターゲット▽ポジション-の3つ。その中でも特に重視したのが「劇的救命」と呼ばれるコンセプトだ。「救命不能に思われるような重症者も、鮮やかに劇的に回復させる」。こんな思いが「劇的救命」という言葉には込められている。
講演の中で今氏は、海に流された40歳代女性の「劇的救命」を紹介した。同病院ではドクターヘリを整備するが、運行は日中のみ。夜間は長時間の陸路搬送になることもあることから、手術室をドクターカーにくっつけて現場方向に出発。現場から病院へ向かう救急車と途中の道路でドッキングし、そこで緊急手術を開始する。八戸工業大学と共同開発した移動緊急手術室をフェリーふ頭の岸壁に展開し、溺水低体温心肺停止の女性にECMO/PCPSを装着。1カ月後に、この女性は後遺症なく歩けるようになったという。「同様の事例は世界でもフランス・ルーブル美術館前での緊急手術くらい」と話した今氏。こうした経験ができるとして、全国から研修医が集まるようになった。
今氏は、ターゲットに合わせた取り組みを意識するが、「劇的救命」を代表としたネーミングを付けることもその表れ。「サンダーバード作戦」もその一つ。この作戦は、傷病者多数、病院から10-15km付近のエリアにはドクターヘリとドクターカーが同時出動するというもの。もちろん1秒でも早く処置を開始し、素早く病院へ搬送するためのものだが、こうしたネーミングにさえ気を配りながら、日本有数の救命救急センターを作り上げた。
ブランド化に成功した結果、医療従事者を全国から集めることにつながった。救急医は今氏1人から19人に、総医師数は89人が168人に増えた。救急を学びに来た研修医が、外科や内科に進み、専門医が増え患者への対応が充実する好循環で、病院の経営が改善したという。「医師数は収益に影響する」と今氏は振り返り、正職員全体で見ても11年に694人だったのが、22年には1,172人に増やしたと説明。これは八戸市の正社員雇用を430人、給与は10.4億円増やしたことになり、「地域経済の循環にもつながった」と胸を張った。
医療介護経営CBnewsマネジメント
【関連記事】
【関連キーワード】












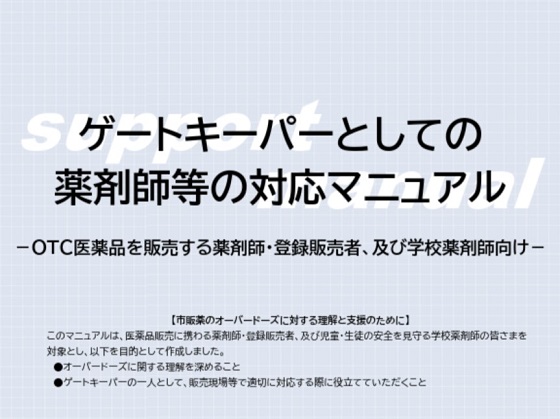









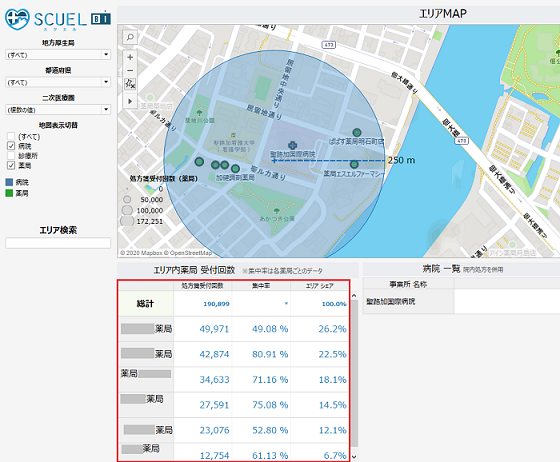









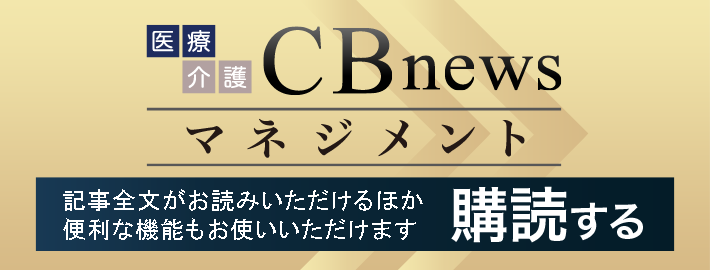
.jpg)


