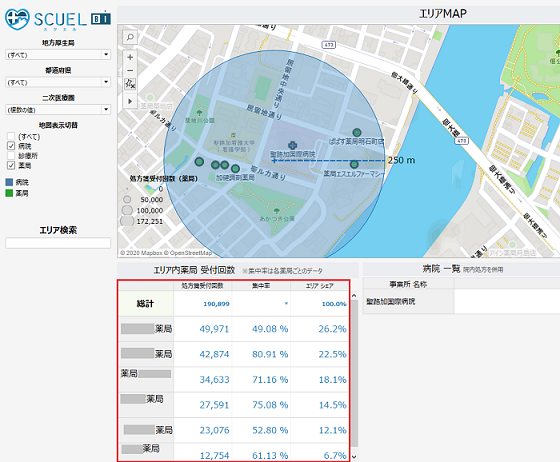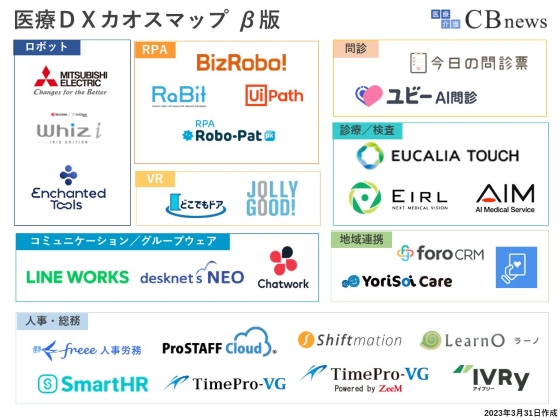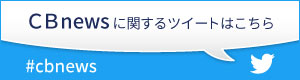強い地域薬局を、まちの灯りになるために
M&Aのかたち・ケース2

強い薬局をつくることが地域への貢献につながると話す秋野社長
「なの花薬局」などを全国で354店舗(今月1日現在)展開する、株式会社ファーマホールディング(札幌市中央区)の秋野治郎・代表取締役社長には、子どものころに見た忘れられない光景がある。北海道に台風が直撃した1954年9月、生まれ育った小樽の街は電気などライフラインが寸断され真っ暗闇に。しかし、医薬品卸業を営んでいた実家にあった米軍払い下げのガソリンランタンの光の下に、薬を求める地域住民が集まって来た。「災害などの極限状態でも“まちの灯り”になりたい」-。薬剤師になった秋野社長は、これまでその一心で、M&Aなどを行いながら強固な経営基盤を築き上げてきた。【聞き手・丸山紀一朗】
【関連記事】
薬局業界は、これから真の意味で「かかりつけ薬局」になっていくことを目指すべきです。今、海外に行って日本の医薬分業の仕組みを話すと、「そんなにいびつな状態なのか」などと驚かれますし、そもそも日本語の「門前薬局」や「調剤専門薬局」の訳語は外国語にありません。今後、国の財政との関係から考えても、本当に地域に必要とされる薬局だけが生き残っていくでしょう。
国際的な「薬局」の概念は2つしかありません。「コミュニティー・ファーマシー」(地域薬局)か「クリニカル・ファーマシー」(院内薬局)です。私たちは前者の地域薬局を目指しており、「調剤薬局」という言葉は極力使わないことにしています。そこには、薬局はもっといい仕事ができるし、より面白い取り組みもできるし、さらに世の中のためになれるのだという考えがあるからです。これが当社の根幹にある考え方です。
■地域薬局は過疎地で真価を発揮する
今後、地域薬局の存在感が出てくるのは、地方など過疎地になるでしょう。これは米国ですでに起きています。例えば私は先日、米国の薬局でインフルエンザのワクチンを接種してもらいました。コミュニティー・ファーマシスト(地域薬剤師)がやるのです。なぜ米国でそういうことができるかというと、インディアンの領有する土地、すなわち過疎地から医療関係者が撤退し、そこに残った住民の健康を守ろうと手を挙げたのが薬剤師だったからなのです。
医療介護経営CBnewsマネジメント
【関連記事】